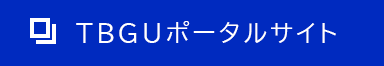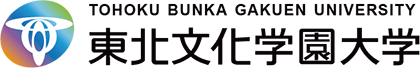| 文字サイズ |
|---|

キャンパス案内
vol.1 学生が相談に来たとき、どのように対応すればいいですか
Q. 学生が相談に来たとき、「自分の話をちゃんと聞いてもらえた」と学生が納得し、その後の成長につながるような対応をしたいと考えています。どうしたらよいでしょうか。
A. 学生が教職員に相談するというのは、「うまく伝えられるだろうか」「否定されないだろうか」など、教職員の想像以上に勇気のいる行動です。そんな中、自主的に相談に来たり呼び出しに応じたりした学生には、話しやすい雰囲気で接したいものです。「よく来てくれましたね」という労いの言葉や「雨が続きますね。寒くないですか」という他愛のない挨拶は、空気を和らげる効果があります。
相談の時間は、学生にとって自分自身のことを静かに考える貴重な機会でもあります。「話を聴きたい」「一緒に具体的に考えていきたい」というこちらの気持ちがきちんと学生に伝わるよう心掛けたいものです。途中で色々とアドバイスしたくなる気持ちは一旦横に置き、まずは話をさえぎらず、最後まで聞きましょう。
聞く側の表情や声も重要です。腕や足を組んだり、ふんぞり返った姿勢は、学生に威圧感を与え、話す意欲を低下させる可能性があります。相槌を打ったりうなずいたりしながら一通り話を聴いた後に、「○○ということなのですね」と要約して伝えると、学生は「話を受けとめてもらえた」とホッとした気持ちになるようです。このような体験の積み重ねが、この先困難を乗り越えていく学生の力になります。
また、面談開始時に何時まで(何分ぐらい)時間が取れるかを伝えておく方が、学生は安心して話ができます。授業の直前や遅い時間帯に急に来室する学生もいるでしょう。その場合は、学生に「じっくりと話を聴きたい」という気持ちを伝え、次に会う約束をしましょう。緊急性が高い場合や一人で抱えるには重すぎる相談内容の場合、「他の教職員と一緒にあなたを支えていきたい」という思いを伝え、本人の了解を得ておくとよいでしょう。
すぐに問題が解決しないときは「一緒に問題について考えていきたい。また〇日後に来てもらえたらと思うが、どうか」と伝えてみましょう。次の約束は、学生の安心に繋がります。そして相談終了後も、学生の様子を見守っていただければと思います。
ポイント
①一緒に考える姿勢を示す。
②目の前の学生をありのままに受容し、変化をサポートする。
③時間の設定をする。
④経過を見守る。
A. 学生が教職員に相談するというのは、「うまく伝えられるだろうか」「否定されないだろうか」など、教職員の想像以上に勇気のいる行動です。そんな中、自主的に相談に来たり呼び出しに応じたりした学生には、話しやすい雰囲気で接したいものです。「よく来てくれましたね」という労いの言葉や「雨が続きますね。寒くないですか」という他愛のない挨拶は、空気を和らげる効果があります。
相談の時間は、学生にとって自分自身のことを静かに考える貴重な機会でもあります。「話を聴きたい」「一緒に具体的に考えていきたい」というこちらの気持ちがきちんと学生に伝わるよう心掛けたいものです。途中で色々とアドバイスしたくなる気持ちは一旦横に置き、まずは話をさえぎらず、最後まで聞きましょう。
聞く側の表情や声も重要です。腕や足を組んだり、ふんぞり返った姿勢は、学生に威圧感を与え、話す意欲を低下させる可能性があります。相槌を打ったりうなずいたりしながら一通り話を聴いた後に、「○○ということなのですね」と要約して伝えると、学生は「話を受けとめてもらえた」とホッとした気持ちになるようです。このような体験の積み重ねが、この先困難を乗り越えていく学生の力になります。
また、面談開始時に何時まで(何分ぐらい)時間が取れるかを伝えておく方が、学生は安心して話ができます。授業の直前や遅い時間帯に急に来室する学生もいるでしょう。その場合は、学生に「じっくりと話を聴きたい」という気持ちを伝え、次に会う約束をしましょう。緊急性が高い場合や一人で抱えるには重すぎる相談内容の場合、「他の教職員と一緒にあなたを支えていきたい」という思いを伝え、本人の了解を得ておくとよいでしょう。
すぐに問題が解決しないときは「一緒に問題について考えていきたい。また〇日後に来てもらえたらと思うが、どうか」と伝えてみましょう。次の約束は、学生の安心に繋がります。そして相談終了後も、学生の様子を見守っていただければと思います。
ポイント
①一緒に考える姿勢を示す。
②目の前の学生をありのままに受容し、変化をサポートする。
③時間の設定をする。
④経過を見守る。