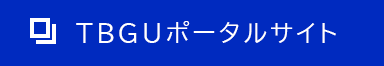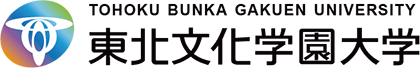| 文字サイズ |
|---|

キャンパス案内
vol.5 学生に学生相談室を勧めたいとき、気を付けることはありますか
Q. 授業を休みがちだったり、孤立しているように見える学生がいます。声掛けすると、どうやら深刻な悩みを抱えているようです。学生相談室を勧めたいとき、どのようなことに気を付けるとよいでしょうか。
A. 学生は「この先生(職員)なら信頼できる」という気持ちがあって話してくれています。まずは真摯に話を聴くことが大切です。その際、社会的常識、助言、説得などは不要です。学生の気持ちを否定しないようにしましょう。
また、プライベートなことは深く聞き過ぎない方がベターです。教員の役割の一つは「評価すること」です。「評価する・される関係」と「心の問題に共同で取り組む関係」は両立が難しいものです。中立的な立場で学生と向き合うことのできる学生相談室へ早めにバトンタッチできるとよいと思います。
相談室を勧めるには工夫が必要です。一例として、以下のことが考えられます。
①学生から「見捨てられた」と誤解を受けない伝え方をする。
(「力になってくれる人を増やそう」「よかったら一緒に行こう」)
②学生相談室の情報を教える。
(「教員とは違う立場から話を聴いてくれるカウンセラーがいるよ」「あせって結論を出すよりも、カウンセラーに話して気持ちを整理してみてはどう?」)。
学生が相談室へ行きたがらない場合、「人に頼るのはダメなこと」「相談内容が外部に漏れるのではないか」などの誤解がある可能性もあります。その場合は、「相談の結果、決断するのはあなた自身。相談は、自立の助けとなる行動だよ」「あなたの了承なしにカウンセラーが情報を漏らすことはないよ」と伝えてみてください。それでも学生が「行きたくない」という場合は、無理強いをしないでください。教員との信頼関係を維持することが一番大切です。あるいは、一度学生相談室までご案内いただくだけでも結構です。
抑うつや無気力など、青年期はメンタルの不調をきたしやすい時期です。早期に専門機関につなぐことが大切です。学内機関である学生相談室であれば、その後の連携協働もしやすくなります。
また、プライベートなことは深く聞き過ぎない方がベターです。教員の役割の一つは「評価すること」です。「評価する・される関係」と「心の問題に共同で取り組む関係」は両立が難しいものです。中立的な立場で学生と向き合うことのできる学生相談室へ早めにバトンタッチできるとよいと思います。
相談室を勧めるには工夫が必要です。一例として、以下のことが考えられます。
①学生から「見捨てられた」と誤解を受けない伝え方をする。
(「力になってくれる人を増やそう」「よかったら一緒に行こう」)
②学生相談室の情報を教える。
(「教員とは違う立場から話を聴いてくれるカウンセラーがいるよ」「あせって結論を出すよりも、カウンセラーに話して気持ちを整理してみてはどう?」)。
学生が相談室へ行きたがらない場合、「人に頼るのはダメなこと」「相談内容が外部に漏れるのではないか」などの誤解がある可能性もあります。その場合は、「相談の結果、決断するのはあなた自身。相談は、自立の助けとなる行動だよ」「あなたの了承なしにカウンセラーが情報を漏らすことはないよ」と伝えてみてください。それでも学生が「行きたくない」という場合は、無理強いをしないでください。教員との信頼関係を維持することが一番大切です。あるいは、一度学生相談室までご案内いただくだけでも結構です。
抑うつや無気力など、青年期はメンタルの不調をきたしやすい時期です。早期に専門機関につなぐことが大切です。学内機関である学生相談室であれば、その後の連携協働もしやすくなります。
ポイント
①まずは真摯に話をきく。
②ただし、心の奥まで深入りしない。
③「あなたが心配」という気持ちを伝えて、勧め方を工夫する。
④その後の連携協働がしやすくなる。
②ただし、心の奥まで深入りしない。
③「あなたが心配」という気持ちを伝えて、勧め方を工夫する。
④その後の連携協働がしやすくなる。