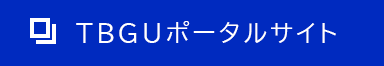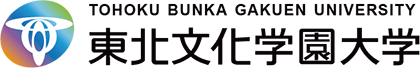| 文字サイズ |
|---|

キャンパス案内
vol.10 学生から「大学に行けません」と言われました
Q. 学生から突然、「大学に行けません」とメールがきました。こういうとき、どうすればよいのでしょうか。
A. 「大学に行けません」と相談されて、その学生を非難したくなる気持ちが湧く方もいるかもしれません。けれども学生の中には、大学に行けない自分自身を「情けない」「普通のことができない無価値な人間」と否定し、無気力スパイラルに陥っている学生もいます。まずは連絡をくれたことを認め、その言葉からは見えづらい背景にも目を向けていくことが大切です。そして、その理由に応じた対応をします。
学力への困り感・劣等感から「自分にはできない、続けられない」と無気力になり、通学が途絶える場合があります。このような学生の場合、「可能な範囲で勉強を教える」「EサポやTA学生等の学習支援先を紹介する」といった実際的なサポートが役立つかもしれません。担当外の講義であれば「教員への質問の仕方を教える」ことも役に立つでしょう。このような「やり方」を教えることは、学生の社会的スキルを磨くことにも繋がります。
友人関係のトラブルから、「同じ教室にいづらい」という理由で大学に来られなくなる学生もいます。このような場合は、席やグループの配慮など、参加できる方法を一緒に考えるとよいでしょう。しかし、具体的な解決策を提案しても、心理的な課題から大学に来られない場合もあります。その場合は、学生相談室と連携するとよいかもしれません。
パニック障害やうつ病などの精神的な問題がある場合、集団に入ることに強い不安を感じることも少なくありません。そのような訴えがあった場合は、席やグループのメンバー、任される役割の割り当てなど、学生と話し合いながら現実的な対応をします。必要に応じて学生相談室や特別支援室の利用を勧めるのもよいでしょう。
「大学に行けません」とのみ話し、事情を説明しない学生もいます。あるいは、「体調不良」とだけ話す学生もいるかもしれません。その場合、教員は「サボリかな」と考えることもあるでしょう。しかし実際には、先に挙げたような理由を、申し訳なさから言い出せない学生もいます。まずはきちんと連絡したことを認めつつ大学に来ることを勧め、「あなたが心配だ。状況とあわせて話を聞かせてほしい」と、直接話すことを重ねて提案してみてください。大学に来られないなら、オンラインや電話で話す方法もあると思います。学生相談室も、オンライン相談や電話相談も受け付けています。
学力への困り感・劣等感から「自分にはできない、続けられない」と無気力になり、通学が途絶える場合があります。このような学生の場合、「可能な範囲で勉強を教える」「EサポやTA学生等の学習支援先を紹介する」といった実際的なサポートが役立つかもしれません。担当外の講義であれば「教員への質問の仕方を教える」ことも役に立つでしょう。このような「やり方」を教えることは、学生の社会的スキルを磨くことにも繋がります。
友人関係のトラブルから、「同じ教室にいづらい」という理由で大学に来られなくなる学生もいます。このような場合は、席やグループの配慮など、参加できる方法を一緒に考えるとよいでしょう。しかし、具体的な解決策を提案しても、心理的な課題から大学に来られない場合もあります。その場合は、学生相談室と連携するとよいかもしれません。
パニック障害やうつ病などの精神的な問題がある場合、集団に入ることに強い不安を感じることも少なくありません。そのような訴えがあった場合は、席やグループのメンバー、任される役割の割り当てなど、学生と話し合いながら現実的な対応をします。必要に応じて学生相談室や特別支援室の利用を勧めるのもよいでしょう。
「大学に行けません」とのみ話し、事情を説明しない学生もいます。あるいは、「体調不良」とだけ話す学生もいるかもしれません。その場合、教員は「サボリかな」と考えることもあるでしょう。しかし実際には、先に挙げたような理由を、申し訳なさから言い出せない学生もいます。まずはきちんと連絡したことを認めつつ大学に来ることを勧め、「あなたが心配だ。状況とあわせて話を聞かせてほしい」と、直接話すことを重ねて提案してみてください。大学に来られないなら、オンラインや電話で話す方法もあると思います。学生相談室も、オンライン相談や電話相談も受け付けています。
ポイント
①打ち明けてくれたことを認め、理由を尋ねてみる。
②それぞれの理由に応じた対応をする。
③明確な理由を言わない場合でも、見捨てずに細く長く付き合う。
②それぞれの理由に応じた対応をする。
③明確な理由を言わない場合でも、見捨てずに細く長く付き合う。