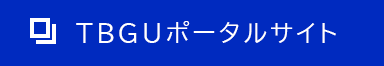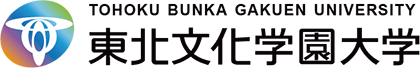| 文字サイズ |
|---|

キャンパス案内
vol.12 学生から「ハラスメントだ」と言われて戸惑っています
Q. 学生につい強い口調で指導をしました。どうやら、その学生が私の指導について「ハラスメントだ」と言っているようです。そんなつもりはありませんが、どう対応すればよいのでしょうか。
A. 学生のためを思った熱心な指導であっても、受ける側の学生が「ハラスメント」と感じる指導は、見直し、変えていく必要があります。例えば、怒鳴るような大声での指導や、「向いていない」などの人格を否定するような言葉に、学生が恐怖心や不快感を感じる場合があります。教員を避ける理由で授業に出席できない、不眠や食欲不振など生活に支障をきたしている場合は、指導方法は改めなければなりません。
まず、学生が自分の指導や関わりをどのように感じたのかについて耳を傾け、学生の気持ちを受け入れる必要があります。もしも双方の受けとり方にズレがあったと分かった場合は、相手が不快に感じない言動に修復していく作業が必要です。関係の修復が困難な場合や学生の希望がある場合は、“指導担当者を変更する”ことも必要かもしれません。このような過程は、当事者である学生と教員だけではなく相談を受けた教職員やその学科・専攻の長などが間に入り、透明性のある形で行われる必要があります。
「自分の感情を抑えられない」など、感情のコントロールが苦手な教員もいるかもしれません。また、ご自身が何らかの精神的ストレスを抱えている場合もあるでしょう。「ハラスメント」と指摘を受けた際には、自分自身の感情コントロール方法や現状について見直すことも重要です。また、日頃から周囲の教職員と相談しあえる関係性を築いておきましょう。
中には「昔の学生は厳しい指導をしても問題がなかった」と主張する教員もいます。しかし、教育方法は時代の流れとともに、今の学生に適した形へ更新されていく必要があります。
学生と意見交換のしやすい風通しのいい雰囲気や関係作りを心掛け、日頃からハラスメント防止に努めましょう。また、「どう指導したらいいか分からない」など指導方法への困り感から「ハラスメント的指導」になることがあります。教職員間で話し合う、必要に応じて学生相談室へ相談するなどして、学生への適切な指導方法を考えるのも良いでしょう。ハラスメントを許容しない大学内の雰囲気作りが大切です。
なお、学生からハラスメントの相談を受けた場合、要望によっては学内のハラスメント窓口を紹介し、学生の訴えにあった対応をしましょう。
まず、学生が自分の指導や関わりをどのように感じたのかについて耳を傾け、学生の気持ちを受け入れる必要があります。もしも双方の受けとり方にズレがあったと分かった場合は、相手が不快に感じない言動に修復していく作業が必要です。関係の修復が困難な場合や学生の希望がある場合は、“指導担当者を変更する”ことも必要かもしれません。このような過程は、当事者である学生と教員だけではなく相談を受けた教職員やその学科・専攻の長などが間に入り、透明性のある形で行われる必要があります。
「自分の感情を抑えられない」など、感情のコントロールが苦手な教員もいるかもしれません。また、ご自身が何らかの精神的ストレスを抱えている場合もあるでしょう。「ハラスメント」と指摘を受けた際には、自分自身の感情コントロール方法や現状について見直すことも重要です。また、日頃から周囲の教職員と相談しあえる関係性を築いておきましょう。
中には「昔の学生は厳しい指導をしても問題がなかった」と主張する教員もいます。しかし、教育方法は時代の流れとともに、今の学生に適した形へ更新されていく必要があります。
学生と意見交換のしやすい風通しのいい雰囲気や関係作りを心掛け、日頃からハラスメント防止に努めましょう。また、「どう指導したらいいか分からない」など指導方法への困り感から「ハラスメント的指導」になることがあります。教職員間で話し合う、必要に応じて学生相談室へ相談するなどして、学生への適切な指導方法を考えるのも良いでしょう。ハラスメントを許容しない大学内の雰囲気作りが大切です。
なお、学生からハラスメントの相談を受けた場合、要望によっては学内のハラスメント窓口を紹介し、学生の訴えにあった対応をしましょう。
ポイント
①学生の言い分や気持ちを、反論せずに、よく聞く。
②自分の感情パターンや問題、指導方法を見直す。
③日頃から、ハラスメント防止を心がける。
④学内のハラスメント相談窓口を利用する。
②自分の感情パターンや問題、指導方法を見直す。
③日頃から、ハラスメント防止を心がける。
④学内のハラスメント相談窓口を利用する。