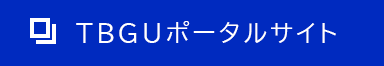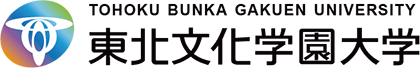| 文字サイズ |
|---|

キャンパス案内
vol.15 入学させたら卒業までが大学の義務?
Q. 学生の家族へ成績不良、単位習得の難しさについて話をしたところ、「入学させたのだから、卒業させるのが大学の義務だ」「救済措置はないのか」と強く迫られました。どう対応すればよいのでしょうか。
A. 年々、履修の遅れや出席不良、成績不振に悩むケースが増えています。まれに保護者から「入学させたのだから卒業まで責任をもってほしい」「救済措置はないのか」という強い訴えを受けることもあります。
私たちは大学を「教育機関」として理解していますが、保護者の一部には「大学=サービス提供機関」との誤解が根強くあります。「入学=卒業の保証」ではなく、「入学=学ぶ機会の提供」であり、「卒業はあくまで一定の学修成果を修めたことへの証明」であることを対外的にも内部的にも再確認する必要があります。
大学には、学生が学びやすい環境を整える責任はありますが、「本人が努力しなくても卒業できるようにする責任」はありません。その線引きを明確にしておかないと、支援が「免責の手段」と誤解され、教職員が疲弊する結果を招きかねません。
なお、合理的配慮の対象ではなくとも、困難を感じている学生に「支援的関わり」を行うことは可能です。例えば、生活リズムの整え方のアドバイス、履修相談の強化、提出期限のリマインド、学生相談室による定期的な見守りなど、教育的意義のある支援はいろいろ考えられます。
しかし、「出席しなくても単位がもらえる」「成績が悪くても卒業できる」といった「制度の根幹を曲げる要求」は、支援ではなく「特別扱い」に近くなります。そのような対応が一部の学生だけに行われれば、教育の公平性が損なわれ、かえって全体の信頼を失うリスクがあります。
学生を「守る」ことと「育てる」ことは時に背反するように見えますが、どちらも「学生の自律した社会的成長」という同じ目的に向かっています。私たち教職員もまた、可能な範囲でケース検討会などを実施し、孤立せず、連携しながら対応していきたいものです。
私たちは大学を「教育機関」として理解していますが、保護者の一部には「大学=サービス提供機関」との誤解が根強くあります。「入学=卒業の保証」ではなく、「入学=学ぶ機会の提供」であり、「卒業はあくまで一定の学修成果を修めたことへの証明」であることを対外的にも内部的にも再確認する必要があります。
大学には、学生が学びやすい環境を整える責任はありますが、「本人が努力しなくても卒業できるようにする責任」はありません。その線引きを明確にしておかないと、支援が「免責の手段」と誤解され、教職員が疲弊する結果を招きかねません。
なお、合理的配慮の対象ではなくとも、困難を感じている学生に「支援的関わり」を行うことは可能です。例えば、生活リズムの整え方のアドバイス、履修相談の強化、提出期限のリマインド、学生相談室による定期的な見守りなど、教育的意義のある支援はいろいろ考えられます。
しかし、「出席しなくても単位がもらえる」「成績が悪くても卒業できる」といった「制度の根幹を曲げる要求」は、支援ではなく「特別扱い」に近くなります。そのような対応が一部の学生だけに行われれば、教育の公平性が損なわれ、かえって全体の信頼を失うリスクがあります。
学生を「守る」ことと「育てる」ことは時に背反するように見えますが、どちらも「学生の自律した社会的成長」という同じ目的に向かっています。私たち教職員もまた、可能な範囲でケース検討会などを実施し、孤立せず、連携しながら対応していきたいものです。
ポイント
①保護者への対応は「誠実に丁寧に、しかし揺るがず」。
②「大学としてできる支援を模索する一方、本人の努力が不可欠である」ことを丁寧に、繰り返し伝える。
③必要に応じて、学生相談室などの支援先を紹介する。
②「大学としてできる支援を模索する一方、本人の努力が不可欠である」ことを丁寧に、繰り返し伝える。
③必要に応じて、学生相談室などの支援先を紹介する。