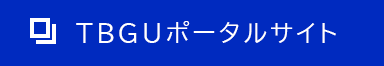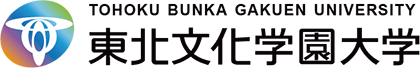高校までに習った数学が理学療法の世界でどのように生かされているのか学びます。基礎から徹底的に学び,自らの力で解答を導き出せることを目標にしています。
| 文字サイズ |
|---|

医療福祉学部 理学療法学専攻
TOP > 学部学科・大学院 > 理学療法学専攻 > 学習の流れ > 授業紹介|理学療法学専攻
授業紹介
基礎数学
アカデミック・スキル演習
理学療法士に求められる情意領域の基礎を培うことを目的に,グループ学習や学習ポートフォリオの記入を通じて,一人一人が考察し,理学療法学学生としての基礎的素養を身に付けます。
 |  |  |
解剖学(Ⅰ・Ⅱ、解剖学実習)
人体の構造を肉眼解剖学と顕微解剖学のレベルから学びます。実習では骨スケッチや筋・腱の貼りつけ等を行い理解を深めます。
 |  |  |
基礎運動学
ヒトの運動・動作を理解する上で基礎となる物理的知識(特に力学)を学びます。
 |  |
身体運動学演習
解剖学・運動学の知識をベースに主にヒトの関節運動の仕組みについて学びます。
 |  |
リハビリテーション概論
チーム医療とは何ぞや?を理解する契機となる授業とリハビリテーションを実施する際の報酬について学びます。
理学療法学概論
人間学の視点から理学療法・理学療法士の仕事について学びます。人間学とは「人とは何か、人はいかに生きるべきか」を問う学問です。理学療法は治療学的側面とリハビリテーション医療における社会復帰支援という二つの側面を有しています。いずれにしろ、患者を生活者として全人的にとらえることが必要となります。その意味で、理学療法士としての心がまえを深く考えることがこの科目の目的です。
 |  |
理学療法学基礎演習(Ⅰ・Ⅱ)
障害レベルに応じた理学療法評価と基本的介入の視点について、演習を通して入門的に学びます。主に理学療法評価、運動療法、物理療法、日常生活活動と生活環境への介入、義肢・装具等について体験・実習します。また、理学療法士は対象者に対して運動を治療手段として用います(運動療法)。その運動によって生体はどのような変化を起こすのかを、運動生理学の視点から学びます。
理学療法評価技術演習(Ⅰ・Ⅱ)
理学療法士が行う各種の検査・測定・試験等を素早く正確に実施する技術を身につけることを目標にした授業です。解剖学、生理学、運動学を基礎として、身体および身体運動の計測を実習します。
 |  |  |
基礎セミナー(Ⅰ~Ⅳ)
1年生は理学療法技術の基礎(検査測定技術・介助技術)を2年生から教わり、2年生は1年生へ教えることで理学療法技術の基礎を自ら学びます。
 |  |  |
夏季集中セミナー
岩手県久慈市に3泊4日で行う宿泊型のセミナーになります。理学療法士となるために社会で求められる知識や技術に加え,医療人としての態度や意識づくりを目的に夏季集中セミナー(3泊4日の合宿)を行います。
 |  |  |  |
身体運動学実習
ヒトの運動・動作に関する身体運動学的メカニズムについて,筋電図,歩行などの実習形式で計測したデータを基に結果を考察し,身体運動の原理について理解することを目的とします。
 |  |
理学療法管理学
病院や組織の中そして地域で行われるリハビリテーション関連業務について、実際の仕事や運営などについて学びます。
運動動作分析演習
身体運動学・運動制御論で学んだ基礎知識をもとに、臨床における運動動作分析の意義と技術を習得し、多様な動作パターンを適切に分析できることを目標とします。
臨床動作分析演習
さまざまな障害がある場合、特に身体運動に障害がある場合の動作分析を学びます。1年次後期から2年次前期で学んだ身体運動学の知識をもとに、基本的な日常生活における動作を対象として観察と分析、およびその記録について演習を行います。
運動器理学療法演習(Ⅰ~Ⅲ)
運動器に障害を呈する各種疾患の特性に応じた理学療法評価と介入法について、講義と実習を通して学習します。演習Ⅲでは、講義を通して習得した知識を基に、実際の患者様を想定したケーススタディを実施します。
小児理学療法演習(Ⅰ・Ⅱ)
演習Ⅰでは、新生児が二足歩行を獲得するまでの定型運動発達の過程を中心に身体運動学の視点から学びます。続く演習Ⅱでは、脳性麻痺や進行性筋ジストロフィーなど小児領域の疾患の基礎知識や、理学療法について学びます。また特別講義として、筋ジストロフィーを専門に治療されている理学療法士の先生にご講義いただき、臨床での視点なども学習していきます。
神経理学療法演習(Ⅰ~Ⅲ)
脳の構造理解やCT・MRIなどの画像診断を通し、多様な脳血管障害の病態を理解します。加えて、脳卒中片麻痺の評価を、講義・演習を通して学ぶことにより、臨床における姿勢観察の基本、姿勢制御の特徴および原因について分析できることを目標とします。演習Ⅱ・Ⅲでは、脳卒中片麻痺やパーキンソン病、神経筋疾患などの各種疾患の評価から治療実施までの理学療法を学びます。
 |  |  |  |
内部障害理学療法演習(Ⅰ~Ⅲ)

内部障害患者にかかわる基本的な解剖・生理学、病態生理を学び、各種疾患に対する理学療法評価・治療についての理解を深めます。演習Ⅰでは循環器疾患、演習Ⅱでは代謝疾患・がん、演習Ⅲでは呼吸器疾患をそれぞれ中心的に学習します。超高齢社会に伴い増加を続ける各種内部疾患を合併した対象者に対応できる能力を養うことを目標とします。
総合理学療法学演習
学科専攻で学ぶ理学療法領域に収まらない分野(熱傷、疼痛、失語症、摂食嚥下、視覚障害、精神心理、複合疾患など)について学びます。
義肢装具学実習
2年次の義肢装具学で学んだ義肢と装具の基本構造と機能についての知識を基に、実習を通して各種機具の適合判定や処方を学びます。実習では、義肢装具士の方の指導の元、実際に下肢装具を作成したり、特別講義として実際に大腿・下腿切断で義足を使用している方をお招きしご講演頂くことで、臨床での義肢・装具に対する理学療法士としての視点や関わりを学びます。
物理療法学実習
物理療法とは、温熱、寒冷、電気、光線、牽引などの物理的手段を用いて治療するものです。
物理療法学実習では、2年次後期の講義で学んだ知識を基に、臨床現場で患者に実施する際の注意点などを、学生自らの体験・実践を通して学びます。また、物理療法を実施した際の効果や結果を科学的に考察していきます。
物理療法学実習では、2年次後期の講義で学んだ知識を基に、臨床現場で患者に実施する際の注意点などを、学生自らの体験・実践を通して学びます。また、物理療法を実施した際の効果や結果を科学的に考察していきます。
日常生活活動演習(Ⅰ・Ⅱ)
日常生活活動にかかわる評価法やリハビリテーション支援機器を用いた介入技術などを講義・実習を通して学びます。実習では、杖や車いすといった移動補助具、自助具や環境制御装置など日常生活活動に関わる機器を実際に用いて、具体的な活用方法を学びます。さらに保健福祉学科の教員の指導の元、医療・介護分野で従事する職種として、介助用おむつの使用方法や排せつの介助・指導についても学びます。
 |  |  |
地域理学療法学演習(Ⅰ・Ⅱ)
障害児・者や高齢者などの方々が地域で生活していくうえでの法律、制度などを学びます。施設や事業所などで働く理学療法士が在宅生活している対象者の方々に関わること(評価・治療など)を学びます。地域生活している方々の健康増進・介護予防、災害支援などにも理学療法士が関わることを学習します。
 |  |
スポーツ理学療法セミナー
ストレッチングや筋力トレーニング,テーピングなどスポーツ領域における理学療法士の役割を実技を通して学んでいきます。さらに各種スポーツ疾患に対する理学療法を系統的に学びます。
医学英語
医学や医療の中で使われる英語の専門用語を学びます。
理学療法学特論
理学療法に関わる研究について実践を通して学ぶ科目です。3年次から少人数グループに分かれて研究を進め、4年次後期の成果報告会で発表します。
 |  |  |