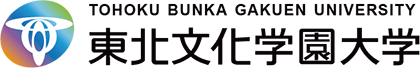酒造りの歴史②
2020.1.8
総合政策学部准教授 渡邊洋一
総合政策学部准教授 渡邊洋一
(前回の続き)
2.古代の酒
『古事記』『日本書紀』『風土記』等の古代の書物には酒の記事は随所に出てくる。しかし、その大半は神話の域を出ない部分の記述である。例を挙げると須佐能男尊(すさのおのみこと)の八俣遠呂知(やまたのおろち)退治の時に八塩折酒(やしほりのさけ)を醸させた事や前述の木花開耶姫が天孫の御子を生んだ時に天甜酒(あまのたむさけ)を作った事等があるが、ここで注目したいのが八塩折酒にしろ天甜酒しろ記事の内容からいって材料は米でしかもその生成法は麹黴による醗酵で作られるのではなく、米を人が口の中で噛み砕き、それを器の中に溜めて醗酵させて作ったとみることが出来、これが日本における最初の酒造方法であったということが伺える。
このことは『大隅国風土記逸文』中に「大隅ノ国ニハ、一家ニ水ト米トヲマウケテ、村ニツゲメグラセバ、男女一所ニアツマリテ、米ヲカミテ、サカブネニハキイレテ、チリヂリにカエリヌ。酒ノ香ノイデクルトキ、又アツマリテ、カミテハキイレシモノドモ、コレヲノム。名ヅケテクチカミノ酒ト云フト云々」(『塵袋』第九掲載)とあることからも実証される。現在でも南島の一部には祭の際の御神酒は処女に噛ませて造らせる所があり、それはこの名残ではないかと思われる。
ところが、応神・仁徳朝期(4~5世紀頃?)大陸から酒造法の新技法が渡来してきたことが『古事記』や『新撰姓氏録』に記されており、これがおそらく麹をねかせて醸造する現在の酒造りのルーツにあたる製法であったとされる。その方法が応神・仁徳朝期の伝来か否かということは実証出来ないものの、6世紀以降の大和朝廷が中央集権的国家体制を模索しながら次第に中国でいう“東海の小国倭”から“日本”へと変貌していく中、酒造りの歴史も“稲の国の稲の酒”として現在の日本酒の形態を整えていく。
これは「稲」と「稲の酒」とを神事の中心に添えた日本の国事の中、酒が中心的役割を果たすことになったことを意味し、そのために国家では律令体制が整った後に“酒造司(みきのつかさ)”なる職を設け、国事で用いる酒を賄い、ここに“天皇の酒”が完成することになる(清酒が出来るのは近世以降)。
酒造司は国事用の酒を調達するのが役割であるから宮内庁所管で、実際に酒造りに従事するのは都のある大和及び隣接の河内・摂津の酒戸(さかへ・さけこ)と呼ばれる百八十五戸の集団で、これが現在の“杜氏”の始まりであろう。
本来、酒というのは国事の折にのみ用いられる神聖なものであったといえようが、それはそれ世界の何処でもそうであるが、一般へ浸透していくのも早かったと思われる。特に荘園が出来、王侯貴族達が広大な私有地を持つようになると、そこで造られた余剰米を使って酒造りを始めるのは当然であり、そうした状況下では酒造司配下の大和・河内・摂津の酒戸たちもそうした荘園の酒造りの中に拡散していくことになるのは道理である。
つまり古代において宮中における「神々の酒・天皇の酒」は飛鳥・藤原・奈良・平安と時代を経、当初は厳格に守られていた律令制による規律が次第に緩んでくると、“酒”は共に宮廷の神事を司る皇室系の神社(大神宮等)から各豪族の氏神の諸神社へ、また広大な荘園を有する貴族階級や大寺院の傘下へと拡大し、さらに民間へと拡散していくことになる。
そうした中、民間への酒の売買も八世紀には始まり(『釋日本紀』に高麗人が市で旨酒を売っていたとの記録がある)、平安時代になると有力寺院や地方豪族のうちで酒を売ることを半ば生業とした者が現れ、中には暴利を貪った者もいたことが『今昔物語』や『日本霊異記』といった書物の中にもその類の記述が見えてくる。概して、平安時代の貴族階級等の知識人は正式な宮中行事の折りには酒造司で造られた正規な酒を飲んでいたのは勿論であるが、正規な行事における飲酒にはそれなりのしきたりがあって堅苦しいものであったことが伺えることから、それとは別に普段は自領の荘園より上がった酒を飲みながら遊興に耽っていたことが推測される。
勿論、当時の酒は製造法がお粗末でアルコール度数は低く、アルコール化出来なかった糖類がそのまま残る現代の酒から比べものにならないくらい甘い酒であったため、毎日のように酒に耽っていた豪族・貴族たちの中に酒の害がなかったはずはなく、古くは奈良時代の歌人で「酒讃歌」十三首を『万葉集』に残している大伴旅人(『万葉集』の編者と目されている大伴家持の父)や同じく『万葉集』の中に「貧窮問答歌」を残している山上憶良等は現在でいうアルコール中毒・依存症であったようだし、平安時代の貴族の中には明らかに現在でいう糖尿病的な症状等を呈していた者も多く見られ、中には酒乱で殺傷沙汰を起こしている記録もある。現代とは異なり衛生観念が低く、医療状況がお粗末であった当時においては早世する原因の一つに飲酒の習慣が挙げられかねない状況であった。現に一条天皇の摂政・関白を勤めた藤原道隆(藤原道長の兄で、娘定子は一条天皇の皇后)は飲酒が原因となる糖尿病の悪化に余病を併発して死亡したと推定されている。
それでは、こうした状況下において、当時の人々はどの様な酒を飲んでいたのであろうか。平安時代前期の延喜13年(913)に編纂された『延喜式』により、宮中の酒造司における代表的酒造りの特色を挙げてみよう。
この内、①は正式な宮中の行事の折に用い、②は盛夏用、③は正月用の儀式酒で④以下は普段嗜む酒といってよかろう。その他もっと質の落ちる粕酒(御酒等の絞り粕に水をさして造ったもの)等があり、その地位に応じて嗜んでいたことが伺える。
(以下 次号)
2.古代の酒
『古事記』『日本書紀』『風土記』等の古代の書物には酒の記事は随所に出てくる。しかし、その大半は神話の域を出ない部分の記述である。例を挙げると須佐能男尊(すさのおのみこと)の八俣遠呂知(やまたのおろち)退治の時に八塩折酒(やしほりのさけ)を醸させた事や前述の木花開耶姫が天孫の御子を生んだ時に天甜酒(あまのたむさけ)を作った事等があるが、ここで注目したいのが八塩折酒にしろ天甜酒しろ記事の内容からいって材料は米でしかもその生成法は麹黴による醗酵で作られるのではなく、米を人が口の中で噛み砕き、それを器の中に溜めて醗酵させて作ったとみることが出来、これが日本における最初の酒造方法であったということが伺える。
このことは『大隅国風土記逸文』中に「大隅ノ国ニハ、一家ニ水ト米トヲマウケテ、村ニツゲメグラセバ、男女一所ニアツマリテ、米ヲカミテ、サカブネニハキイレテ、チリヂリにカエリヌ。酒ノ香ノイデクルトキ、又アツマリテ、カミテハキイレシモノドモ、コレヲノム。名ヅケテクチカミノ酒ト云フト云々」(『塵袋』第九掲載)とあることからも実証される。現在でも南島の一部には祭の際の御神酒は処女に噛ませて造らせる所があり、それはこの名残ではないかと思われる。
ところが、応神・仁徳朝期(4~5世紀頃?)大陸から酒造法の新技法が渡来してきたことが『古事記』や『新撰姓氏録』に記されており、これがおそらく麹をねかせて醸造する現在の酒造りのルーツにあたる製法であったとされる。その方法が応神・仁徳朝期の伝来か否かということは実証出来ないものの、6世紀以降の大和朝廷が中央集権的国家体制を模索しながら次第に中国でいう“東海の小国倭”から“日本”へと変貌していく中、酒造りの歴史も“稲の国の稲の酒”として現在の日本酒の形態を整えていく。
これは「稲」と「稲の酒」とを神事の中心に添えた日本の国事の中、酒が中心的役割を果たすことになったことを意味し、そのために国家では律令体制が整った後に“酒造司(みきのつかさ)”なる職を設け、国事で用いる酒を賄い、ここに“天皇の酒”が完成することになる(清酒が出来るのは近世以降)。
酒造司は国事用の酒を調達するのが役割であるから宮内庁所管で、実際に酒造りに従事するのは都のある大和及び隣接の河内・摂津の酒戸(さかへ・さけこ)と呼ばれる百八十五戸の集団で、これが現在の“杜氏”の始まりであろう。
本来、酒というのは国事の折にのみ用いられる神聖なものであったといえようが、それはそれ世界の何処でもそうであるが、一般へ浸透していくのも早かったと思われる。特に荘園が出来、王侯貴族達が広大な私有地を持つようになると、そこで造られた余剰米を使って酒造りを始めるのは当然であり、そうした状況下では酒造司配下の大和・河内・摂津の酒戸たちもそうした荘園の酒造りの中に拡散していくことになるのは道理である。
つまり古代において宮中における「神々の酒・天皇の酒」は飛鳥・藤原・奈良・平安と時代を経、当初は厳格に守られていた律令制による規律が次第に緩んでくると、“酒”は共に宮廷の神事を司る皇室系の神社(大神宮等)から各豪族の氏神の諸神社へ、また広大な荘園を有する貴族階級や大寺院の傘下へと拡大し、さらに民間へと拡散していくことになる。
そうした中、民間への酒の売買も八世紀には始まり(『釋日本紀』に高麗人が市で旨酒を売っていたとの記録がある)、平安時代になると有力寺院や地方豪族のうちで酒を売ることを半ば生業とした者が現れ、中には暴利を貪った者もいたことが『今昔物語』や『日本霊異記』といった書物の中にもその類の記述が見えてくる。概して、平安時代の貴族階級等の知識人は正式な宮中行事の折りには酒造司で造られた正規な酒を飲んでいたのは勿論であるが、正規な行事における飲酒にはそれなりのしきたりがあって堅苦しいものであったことが伺えることから、それとは別に普段は自領の荘園より上がった酒を飲みながら遊興に耽っていたことが推測される。
勿論、当時の酒は製造法がお粗末でアルコール度数は低く、アルコール化出来なかった糖類がそのまま残る現代の酒から比べものにならないくらい甘い酒であったため、毎日のように酒に耽っていた豪族・貴族たちの中に酒の害がなかったはずはなく、古くは奈良時代の歌人で「酒讃歌」十三首を『万葉集』に残している大伴旅人(『万葉集』の編者と目されている大伴家持の父)や同じく『万葉集』の中に「貧窮問答歌」を残している山上憶良等は現在でいうアルコール中毒・依存症であったようだし、平安時代の貴族の中には明らかに現在でいう糖尿病的な症状等を呈していた者も多く見られ、中には酒乱で殺傷沙汰を起こしている記録もある。現代とは異なり衛生観念が低く、医療状況がお粗末であった当時においては早世する原因の一つに飲酒の習慣が挙げられかねない状況であった。現に一条天皇の摂政・関白を勤めた藤原道隆(藤原道長の兄で、娘定子は一条天皇の皇后)は飲酒が原因となる糖尿病の悪化に余病を併発して死亡したと推定されている。
それでは、こうした状況下において、当時の人々はどの様な酒を飲んでいたのであろうか。平安時代前期の延喜13年(913)に編纂された『延喜式』により、宮中の酒造司における代表的酒造りの特色を挙げてみよう。
| NO | 見出し行 | 見出し行 |
|---|---|---|
① | 御酒(みき) | 蒸米・米麹・水を甕に仕込み、十日位してもろみが熟成した段階でこれを絞る。 次に濾別した酒に蒸米・米麹を仕込み、このもろみが熟成した段階でまた絞る。 これを四度繰り返して造った酒で、甘口・濃醇型で、酸の少ない澄み酒 (とはいえ現在の清酒とは異なり、どぶろくの中込みのようなもの)。 |
② | 醴酒(こざけ) | 汲水代わりに酒を用い、米麹の量が多いのが特徴で、 近世初頭の味醂・白酒の原型のようなもの。 |
③ | 三種糟(さんしゅそう) | 味醂系の酒で、大陸渡来の酒。 米麹の他に小麦もやし(麦芽)を併用する所に特徴がある。 |
④ | 頓酒(とんしゅ) 熟酒(じゅくしゅ) 粉酒(こざけ) 汁糟(じゅうそう) | 濁り酒(詳細は不明) |
⑤ | 白酒(しろき) 黒酒(くろき) | 白酒・・・蒸米・米麹・水を甕に仕込んで造った濁り酒 黒酒・・・白酒に臭木(久佐木)の葉の灰を加えて苦みを持たせた酒 |
この内、①は正式な宮中の行事の折に用い、②は盛夏用、③は正月用の儀式酒で④以下は普段嗜む酒といってよかろう。その他もっと質の落ちる粕酒(御酒等の絞り粕に水をさして造ったもの)等があり、その地位に応じて嗜んでいたことが伺える。
(以下 次号)